コインランドリー経営・開業お役立ちコラム

田舎の土地は、活用の仕方によって安定収入や地域貢献につながる資産となり得ます。
一方で、需要の少なさや法規制といった都市部とは異なる課題が多く、戦略的な対応が必要です。
この記事では、田舎で土地活用を成功させるための考え方や注意点、具体的なアイデア14選を紹介し、実現に向けたポイントも具体的に紹介しています。
これから土地活用を検討する方はぜひ参考にしてください。
土地活用とは、使われていない土地や遊休地を有効に利用し、安定した収益や資産価値を生み出す取り組みのことを指します。
具体的には、賃貸住宅の建設や駐車場の運営、倉庫や店舗の貸し出し、さらに太陽光発電設備の設置など、さまざまな手法があります。
ただし、単純に建物を建てれば良いというわけではなく、その地域の需要や立地条件を見極めた上で、最も効果的な活用法を選ばなければいけません。
また、土地活用には初期投資や税金、長期的な運営管理などの課題も伴うため計画性と専門的な知識も必要です。
しっかりと準備を整えれば、遊んでいた土地が将来的な資産へと変わる可能性を秘めています。

田舎にある使われていない土地は、放置しているだけでも固定資産税や維持管理の手間がかかり、所有者にとっては負担になりがちです。
しかし、その土地をうまく活用できれば税負担を軽減できるだけでなく、安定した収益を生む資産に変えられるでしょう。
たとえば、賃貸物件や商業施設として運用することで収入を得られれば、固定費を賄えられます。
また、地域にとっても空き地や空き家が活用されることで、防犯性の向上や景観の改善、雇用の創出などにも寄与し、地域全体の価値向上につながることもあります。
土地活用は個人の利益だけでなく、地域の活性化にもつながる重要な選択肢と言えるでしょう。
田舎の土地は広くて価格も比較的安いことから、一見すると活用しやすそうに思えるかもしれません。
しかし実際はさまざまな要因が障壁となり、思うように活用できないケースも多く見られます。
地域の特性や法的制限、整備にかかるコストなど、事前に確認すべき項目は多岐にわたります。
ここでは、田舎で土地活用するのが難しいと言われる理由を見ていきましょう。
地方の人口は都市部に比べて少なく、交通インフラや商業施設も十分に整っていません。
そのため、住宅や商業施設を建てても、入居者や利用者を十分に確保することができないリスクがあります。
とくに交通の便が悪いエリアでは、集客のハードルが高く事業として成立させるには地域内で本当に必要とされているサービスを見極める必要があります。
需要が限られているからこそ、地域性に合った柔軟な発想が求められます。
関連記事:田舎でコインランドリー経営は儲かる?メリット・デメリットを解説
田舎での土地活用では、法規制も大きなハードルとなります。
都市部と異なり、田舎の土地には多くの地域で都市計画法や農地法など、さまざまな法律がかかっている可能性があるためです。
とくに注意すべきは、市街化調整区域に指定されているケースや、土地が農地として扱われている場合です。
建物の建築や事業内容そのものに制限を与えるため、思い描いた土地活用プランが実現できない可能性があります。
ここでは、「市街化調整区域」と「農地法」について詳しく解説していきます。
市街化調整区域とは、無秩序な開発を抑制する目的で指定されるエリアで、都市計画法に基づき自治体によって定められています。
この区域にある土地は、原則として住宅や店舗などの建物を新たに建てることができません。
たとえ自分の所有地であっても、建築行為には厳しい制限があり、許可を得るまでに多くの手続きや審査が必要になります。
そのため、市街化調整区域で土地を活用したい場合は、建築物を伴わない形での活用が現実的な選択肢となるでしょう。
また、土地の状況によっては個別に許可が必要となるため、計画前に必ず市区町村の都市計画課に確認してください。
農地法とは、農地を守り農業の安定的な運営を目的として定められている法律です。
この法律が適用される土地では、たとえ耕作していない状態であっても、農地としての扱いを受ける限り自由な活用はできません。
つまり、農地を住宅や駐車場、その他の事業用地として使うには、「農地転用」の手続きを踏む必要があります。
農地転用するには自治体の農業委員会に申請し、許可を得る必要があります。
許可を得るまでに通常2〜3ヶ月の期間がかかるほか、審査の内容によっては却下されることもあります。
また、土地が農業振興地域に指定されている場合、原則として農地転用は認められません。
田舎の土地は傾斜地や軟弱地盤など、整地が必要な場所も多く見られます。
過去に建築されたことのない土地では、水道や電気といったインフラ整備も必要になり、その分初期費用もかさむでしょう。
また、造成にあたっては宅地造成等規制法の制約を受ける場合もあり、許可を得なければ工事が進められないケースもあります。
整備コストが高額になればなるほど、投資回収の難易度も上がるため、土地の形状や地盤の状態を事前に把握しておく必要があります。
田舎の土地は広さに余裕がある分、多様な活用方法が考えられます。
都市部と比べると初期投資を抑えやすく、競合も少ないケースが多いため、地域のニーズに合った形で取り組めば十分な収益を見込める可能性があります。
ここでは、実際の成功事例を交えながら、田舎での土地活用におすすめの14のアイデアを紹介します。
田舎では自家用車での移動が一般的なため、毛布や布団など大きな洗濯物を運びやすく、コインランドリーの利用ニーズがあります。
とくに雨天時や花粉の多い季節には、乾燥機の需要が高まる傾向に。
初期費用は機器導入や店舗整備にかかりますが、無人運営が可能でランニングコストも抑えやすいのが特徴です。
土地代が安く競合が少ないエリアであれば、高い集客効果が見込まれます。
関連記事:コインランドリー経営は儲かる?収支シミュレーションと成功の条件を解説
関連記事:コインランドリー経営で失敗しない!費用や業務、始め方の完全ガイド
人口が少ない田舎ではアパート経営が難しいと思われがちですが、労働者が多い工業地帯や農業地帯の近隣であれば、一定の需要があります。
たとえば、外国人技能実習生を受け入れている企業の近くにアパートを建てたことで、企業との借り上げ契約によって、安定した収益につなげている事例もあります。
外部からの流入人口がある地域では、空室リスクを抑えつつ長期経営を目指すことも可能です。
広めの宅地を活かして戸建て賃貸住宅を建てるのも、有効な活用方法の一つです。
相続で取得した土地に2台分の駐車場や小さな庭付きの3LDK住宅を建てたケースでは、固定資産税の軽減も受けられ、長期的な家賃収入につながっています。
アパートのように密集せず、戸建てならではのプライバシーや住環境を重視する入居者にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。
地域に不足している業種を狙って店舗を構える方法も、田舎ならではの土地活用です。
ドラッグストアやコンビニ、カフェなど、日常生活に必要なサービスを提供する店舗は需要が高く、地元の人々の利便性向上にもつながります。
また、幹線道路沿いなど立地に恵まれていれば、ドライブスルー型の飲食店やロードサイド店舗としての展開も考えられます。
自治体の補助制度を活用すれば、初期投資の負担を抑えながら開業できる可能性もあるでしょう。
田舎の広い土地を活かして、貸スペースとして運営する方法も近年注目されています。
古民家や倉庫を改装してレンタルスペースやワークショップ会場にした事例では、地元住民だけでなく都市部から訪れる利用者を取り込むことに成功しています。
また、週末だけイベントスペースとして貸し出すことや、地元のマルシェや地域活動の会場として活用することで、地域との関係性を築きながら安定収入を得られる点も魅力です。
立地や建物の特徴を活かした使い方次第で、個性的なビジネス展開が可能になります。
高齢化が進む田舎地域では、介護施設の需要が着実に高まっています。
既存の医療機関や住宅地が近いエリアであれば、デイサービス施設やグループホームの設置に適しているかもしれません。
実際、空き家だった古民家をバリアフリー改修し、地域密着型の小規模多機能施設として再生させた例もあり、福祉と空き地活用を両立させる成功事例として注目されています。
自治体の補助金や助成制度を活用すれば、初期投資を抑えてスタートできる可能性もあり、将来性の高い事業分野の一つです。
田舎ではまだまだ自家用車中心の生活が主流であるため、駐車場の需要が根強く存在します。
駅や役所、病院、観光地などに近い場所であれば、コインパーキングとして運用することもできます。
住宅街では月極駐車場として貸し出すことで、継続的な収益が期待できるでしょう。
初期費用が比較的少なく済むことから、活用に踏み出しやすい点も駐車場経営の魅力です。
実際に使い道のなかった農地の一部を転用して月極駐車場にした例では、雑草の手入れも減り、維持管理の負担が軽減されたとの声もあります。
自然豊かな田舎の立地を活かして、キャンプ場として整備する選択肢もあります。
近年はアウトドアブームの影響で、都市部から訪れる観光客も増えており、簡易な設備でも一定の需要が見込めます。
元々使われていなかった里山の一部を整備し、テントサイトや焚火スペース、シャワー設備などを設置した事例では、地元食材を使った体験型サービスを組み合わせて付加価値を高めていました。
初期投資を抑えながらも、自然を求める都市部の層をうまく取り込めば、持続的な収益モデルとして展開することも可能です。
都市部からの移住者や、週末農業を楽しみたい人が増えている今、田舎の遊休地を貸農園として活用する取り組みが注目されています。
実際に放置されていた畑を小区画に分けて貸し出した事例では、地元住民だけでなく都市からの利用者も集まり、収益化と地域交流の場づくりに成功しています。
初期費用も比較的低く、必要に応じて水道や簡易な倉庫を整備することで、利用者満足度も高めることができます。
荒れ地や農業をやめた畑を再活用できるため、景観や地域資源の保全にもつながります。
田舎の広大な土地を活かす方法として、太陽光発電設備の設置も有力な選択肢です。
日照時間が長いエリアや、建物を建てにくい傾斜地などでも導入可能で、売電による安定収入を見込めます。
たとえば、使われなくなった農地を転用してメガソーラーを設置した事例では、地域に電力を供給しつつ土地の維持費も賄うことができています。
固定価格買取制度(FIT)の内容や導入コストには注意が必要ですが、初期費用を抑えた小規模ソーラーから始める方法もあり、長期的な活用モデルとして魅力的です。
土地を自ら使うのではなく、他者に貸し出して活用してもらう「土地賃貸」は、管理の手間を最小限にしつつ収益を得たい人に適した方法です。
事業者が店舗用地として借りるケースや、建築会社が資材置き場として活用する例もあります。
実際に、交通量の多い道路沿いの土地を月額契約で貸したことで、継続的な賃料収入が得られたという事例もあります。
用途に応じた契約内容を整えるのがポイントであり、短期貸しから長期貸しまで柔軟に対応できるのがメリットです。
観光地の近くにある田舎の土地であれば、民泊経営も活用法の一つです。
空き家や使われていない住宅を活用すれば初期費用を抑えられ、地域資源を生かした宿泊体験を提供すれば、都市部からの観光客やインバウンド需要の取り込みも期待できます。
自然に囲まれた環境や、静かな時間を求める旅行者にとっては大きな魅力となるでしょう。
民泊には、自宅の一部を貸し出す形と、完全な貸し切り型があります。
後者の場合は管理の手間もありますが、住宅宿泊管理業者に委託すれば遠方からの運営も可能です。
住宅宿泊事業法により営業可能日数は年間180日以内と定められているため、繁忙期や地域のイベント、観光シーズンに合わせて稼働日を調整することで効率的な収益化が見込めます。
物件の清掃やメンテナンス体制、近隣住民との関係づくりなどにも気を配れば、継続的な運営が可能になるでしょう。
近年、働き方改革やテレワークの普及を背景に注目されているのが、サテライトオフィス設置です。
田舎の土地にサテライトオフィスを開設することで、企業にとっては社員の柔軟な働き方を支援でき、地方にとっては雇用の創出や人口流入のチャンスとなります。
実際に一部地域では、企業誘致によって過疎化が進んでいた町が活気を取り戻す例も出てきています。
サテライトオフィスを成功させるには、通信環境の整備や快適な作業空間の設計が大切です。
古民家や空き店舗をリノベーションしてコワーキングスペースや小規模オフィスに転用するケースも多く、立地条件や周辺環境を活かす工夫が求められます。
また、国や自治体による補助金制度を活用すれば初期投資の負担を抑えられ、事業化のハードルも下がります。
活用が難しい土地を無理に使い続けるよりも、条件のよい別の土地へ買い替えるというのも一つの有効な選択肢です。
農地や山林などで法規制が厳しく自由な活用ができない場所を売却し、用途の広い宅地へと資産を移すことで、将来的な運用の自由度が高まります。
収益性の低い土地を手放して利便性の高い場所へ買い替えた上で、賃貸事業に転換することで安定した利益を得ている事例もあります。
売却益や税制上の特例をうまく活用することで、資産の入れ替えがスムーズにできるでしょう。

田舎の土地を有効活用するには、都市部とは異なる視点や準備が求められます。
立地の特性や周辺環境を踏まえて最適な方法を見極めることはもちろん、法規制や資金面、そして実行力のある体制づくりが欠かせません。
ここでは、田舎での土地活用を成功に導くために、押さえておきたい基本的なポイントを6つ紹介します。
土地活用の第一歩は、その土地の特性を正確に把握し、地域のニーズと照らし合わせることです。
人通りが少なく交通の便もよくない場所にアパートや店舗を建てても、空室や空き店舗のリスクが高くなります。
一方で日照条件がよければ太陽光発電、自然環境に恵まれていればキャンプ場などの観光施設といったように、活用方法は土地の特徴に応じて柔軟に変えるべきです。
地域住民の生活スタイルや周辺施設の状況なども含め、現実的な需要を見極めることが成功への近道となります。
関連記事:コインランドリーとの相性が良い!併設に適した業態とは?
土地には都市計画法などに基づいた用途地域の指定があり、建てられる建物や規模に制限が設けられている場合があります。
たとえば、第一種低層住居専用地域では高さ制限や用途制限が厳しく、大型店舗などの建設は不可能です。
また、市街化調整区域や農地に該当する土地では、建築や転用に許可が必要となるケースも多いため、土地活用を始める前に自治体や専門機関で規制内容を調べることが重要です。
思い描いたプランが実行できる土地かどうか、必ず事前に確認しておきましょう。
土地活用は単なる不動産運用ではなく、一つの事業として取り組むべきものです。
初期費用だけでなく、維持管理や修繕、広告費、税金などの経費も含め収支をシミュレーションし、長期的に利益が見込めるか丁寧に検討しましょう。
借入をする場合は返済計画を現実的に立てた上で、リスクに備えた余裕資金の確保も重要です。
利回りの高さだけに目を向けるのではなく、必要な設備投資や空室時の対応まで含め、無理のない持続可能な計画を練ることが求められます。
田舎での土地活用については、自治体や国の補助金制度も上手に活用しましょう。
一例として、サービス付き高齢者向け住宅や地域交流施設などを新設する場合、国土交通省や地方自治体からの支援を受けられるケースがあります。
また、空き家を解体した上で土地を整備するような場合でも、解体費用の一部を助成する制度を設けている地域もあるでしょう。
補助金は地域によって制度内容や申請条件、期限が異なるため、早い段階から情報収集し、自分のプランが該当するか確認しましょう。
関連記事:コインランドリー経営を支援する補助金とは?利用可能な制度を解説
一口に田舎と言っても、自然環境や文化、歴史的背景などは地域によって大きく異なります。
土地活用を成功させるには、画一的なアイデアではなく、その土地がもつ独自の魅力を見出し、地域性にマッチした活用方法を選ぶことが大切です。
たとえば、海や山に近い場所であればアウトドアや体験型の観光施設が向いており、歴史的な建物が残っている地域では民泊や古民家カフェとしての再生も検討できます。
地域の生活者や観光客が何を求めているのか読み解き、そのニーズに寄り添った活用を目指すと、事業が長く続けられます。
土地活用には、不動産・建築・税務・法律など多岐にわたる専門知識が必要です。
初心者がすべてを一人でこなすのは難しいため、信頼できるプロフェッショナルと連携することが成功のカギとなります。
地域に強い不動産会社や施工実績のある建築会社、補助金制度に詳しい行政書士や、税務の専門家である税理士など、分野ごとの専門家に相談しながら進めると安心でしょう。
外注にかかるコストと自力で対応する部分のバランスを取りつつ、無理のない体制を整えたうえで、事業を着実に進めることが重要です。
田舎の土地活用には、地域特性や法規制を踏まえた綿密な計画が不可欠です。
需要を見極めた上で最適な手法を選び、信頼できるパートナーと連携することで、初めて継続的な収益化が見込めます。
ニドコインランドリーでは、現地調査から収支計画、開業後の運営支援までを一貫して対応しています。
田舎の遊休地にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。



| 広さ | 15坪 |
|---|---|
| 立地 | 都市型店舗 マンション1階 |
| 営業形態 | 無人店 |
| 客層 | 主婦・主婦層共働き世帯大洗 |
| 営業時間 | 6:00~24:00 |
| 設置機種 |
乾燥機/ 全自動洗濯乾燥機/ スニーカーランドリー/ |
| ★ポイント | 女性客に喜ばれるドラム式洗濯機を設置クリーンなイメージをアピール |

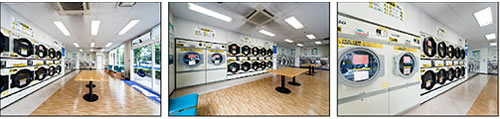
| 広さ | 25.0坪 |
|---|---|
| 立地 | 郊外ベッドタウン、大手スーパー並び |
| 営業形態 | 半有人店舗・プリペイドカードシステム導入 |
| 客層 | 主婦・共働きの大物洗濯、乾燥 |
| 営業時間 | 6:00~23:00 |
| 設置機種 |
乾燥機/ 洗濯機/ |
| ★ポイント | 全面ガラス張りによる明るい店舗設計 有線放送、エアコン完備で快適空間を演出 |
この記事の監修者

横山 秀二 (ヨコヤマ シュウジ)
株式会社ニド 営業部長
《経歴・略歴》
工業高校(機械科)を卒業後、車業界へ就職、その後機械に興味を持ちランドリー業界に転職
《事業への思いや強味》
車業界で機械修理と営業職を行ってきたので、営業+機械修理などの技術職が得意です。
ランドリー業界の仕事も車の仕事と似た所が有り、新規営業などを行いながら機械修理を行うので、営業+機械修理が得意です。また、販売して終わりでなく販売してからが長いお付き合いと思いながら取り組んでおります。